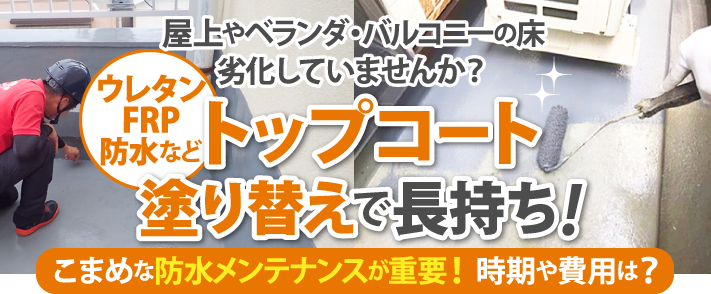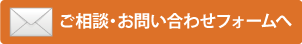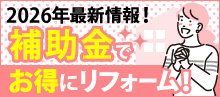文京区白山で床がフワフワする屋上FRP防水を下地からやり直してウレタン塗膜防水の通気緩衝工法で再防水工事しました
【施工前】

【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】
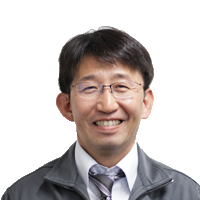
担当:渡辺
文京区白山にお住いのK様は築十五年の木造三階建ての建物にお住まいです。三階の部屋の天井に雨漏りのシミがあるとのことで、私たち「街の屋根やさん」に雨漏り調査のご相談を下さいました。調査にお伺いさせていただき早速、雨漏りをしている部屋を見させていただきました。雨漏りは部屋の隅の部分に起きておりました。天井の広い部分には雨漏りは発生しておりませんでした。雨漏りを起こしている部分を見てみるとどうやら屋上の排水口のあたりと関連がありそうでした。原因を探るために屋上に上がらせていただくと、床面がフワフワとした感触になっております。屋上はFRP防水になっておりました。雨漏りの原因となっている排水口を改修するために再防水工事を行うご提案をさせていただいたのですが、その方法として既存FRP防水を切開し下地を作り直すこともご提案させていただきました。他社様では下地を重ねて再防水を行うという内容だったそうで、私たち「街の屋根やさん」でのご契約・工事を承らせていただくことになりました。
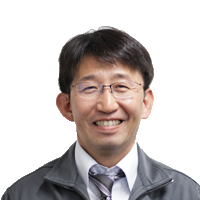
担当:渡辺
- 【工事内容】
- 雨漏り修理 防水工事
- 【工事詳細】
-
- 使用材料
- 施工期間
- 仮設含め実働1週間
- 築年数
- 15年
- 平米数
- 小面積の為、1式扱い
- 施工金額
- 詳しくはお問い合わせください
- お施主様
- K様邸
- ハウスメーカー
- ハウスメーカー不明
- 保証年数
- 10年間
- 【工事内容】
- 雨漏り修理 防水工事
- 【工事詳細】
-
- 使用材料
- AGCサラセーヌ
- 施工期間
- 仮設含め実働1週間
- 築年数
- 15年
- 平米数
- 小面積の為、1式扱い
- 施工金額
- 詳しくはお問い合わせください
- お施主様
- K様邸
- ハウスメーカー
- ハウスメーカー不明
- 保証年数
- 10年間




点検

文京区白山にお住いのK様から、私たち「街の屋根やさん」に雨漏りの件でご相談を頂きました。築年数は15年の木造三階建て住宅で三階の部屋の隅に雨漏りの跡がある、とのことでした。雨漏りの調査ですので、室内を見させていただくことになります。コロナ渦の中での調査となりますのでお客様に新型コロナ感染拡大防止対策をきっちり行っていることをご説明し調査にお伺いさせていただきました。実際に三階の室内をご案内していただきました。すると微かにですが、室内の隅の方に雨漏りの痕跡があるのを確認することが出来ました。部屋の天井を隅々まで確認させていただきましたが雨漏りがあるのは、隅の部分のみのようです。クローゼットの中に天井点検口があったのですが、屋上がある事もあって、桁が邪魔をして天井内部を確認することはできませんでした。K様がおっしゃるには、屋上の床面がフワフワするとのことです。屋上の様子を見ていくことにいたします。


ロフトになっている部分の奥から屋上に出ることが出来ました。屋上はFRP防水をされています。K様がおっしゃられていた通り、一歩足を踏み出した瞬間にわかる「フワフワ感」で部分的になっているのなら経験がありますが、ほぼ全体にわたってフワフワしているのは初めての経験でした。


雨漏りの原因も含めて、屋上を調査していきます。三階の部屋の雨漏り該当部の上は屋上の排水口が絡んでいました。排水口付近には泥が詰まっており内部の状態まで確認することはできません。雨漏りの原因は、この排水口が一番アヤシイのは間違いないのですが、床面全体がフワフワとしてしまっているのは、排水口とは考えにくいところです。フワフワしている感触からいえば当然床面にかなりの雨水が入り込んでいるものと想像できますが、その割に三階の部屋の天井の大部分には漏水痕が無いのも不思議でした。


いずれにしても、再防水工事を行う事は必須の状態である事はK様もご理解されていたようです。問題は「どのように?」「どんな工法で?」という事がK様が気にされていた問題です。他社様はこの上にコンパネを重ねて再防水を行う、というものだったそうです。それではこのフワフワとした状態のままはどうなってしまうのか?というの誰しもが疑問に思うところでしょう。さらに問題なのは、屋上への出口にあるドアの立ち上がりの高さがほぼ無い、という事です。この状態で下地を重ねて施工をしてしまったら、ドアの沓摺と防水面が一緒になり雨仕舞に不安を感じてしまいます。そこで私たち「街の屋根やさん」では、フワフワ感の原因究明も含めて一度防水面を切開し下地の状態も確認しながら、下地を再作成して防水工事を行っていくご提案をさせていただきました。再防水の方法は、ウレタン塗膜防水の通気緩衝工法で行っていくものです。この内容でK様もご了承下さり、ご契約・工事を承らせていただくことになりました。
工事着工

工事は資材の搬入、廃材の搬出等もあるので外部から実施する事になります。そのため建物正面にだけ足場を仮設させていただいての工事となります。
下地の確認・作成

まずは、既存防水面の切開をおこない、下地の状態を確認していきました。建物の構造図面や矩計図があれば構造がわかったのですが、お客様はお持ちでなかったので、想定としてはFRP防水面の下はコンパネが二枚重ねになっていてその下には天井根太が敷かれているものと考えておりました。実際に開口を行ってみるとFRP防水層の下にはコンパネが一枚貼られていて、その下にはシート防水が施されている物でした。


切開をしたところで、あのフワフワとした感触の原因ははっきりとわかりました。下地コンパネがかなりの量の雨水を吸い込んで膨れてしまっていたことにより感じたものでした。切開を行った日は、雨が降った日から、かなり日数も経っていましたが、それでも内部のコンパネはかなり湿っており、コンパネの下のシート防水にうっすらと水たまりができるほどでした。この様子から考えると、FRP防水層に何らかの傷や破損が発生してしまいこのような状態になったのだろうと推測できます。シート防水がなかったら三階の部屋の天井は大な事になっていたのは想像に難しくはありません。やはり下地を作り直すのは正解でした。根太も一部補修が必要になるだろうと想定して用意しておりましたが使わずに済みました。


原因と構造がわかれば、あとは残りの下地コンパネをすべて撤去し、濡れてしまっているシート防水面を乾燥させて清掃を行い、新たな耐水ベニヤを敷設して再防水工事の準備を進めて参ります。
防水工事着手


大工工事の後、防水工事に入りますが、翌日の天候予報があまり思わしくなかったので、いったん雨養生を行って、天候の様子を見ながら本格的な防水工事に入っていきます。三階の部屋の隅の雨漏りの原因となっていた排水口部分には、改修用鉛ドレーンを挿入、設置する予定でしたが、思いのほか配管の内径が細く、あまり人の出入りのない屋上とのことで万が一のオーバーフローも心配があったので、改修用鉛ドレンは設置せずに完璧なシーリングと防水処理を行っていくことになりました。仕様変更となりますのでK様へも状況を説明いたしましてご了承を得てから作業内容を変更しております。


新たに作成し直した下地と既存立上り部分の隙間をシーリングによる防水処理をおこない、プライマーを塗布してウレタン塗膜防水を行っていきます。今回使用する防水塗料は、AGCのサラセーヌを使用していきます。


主剤と硬化剤に別れた二液タイプの防水塗料で規定値通りの分量をしっかりと電動工具で攪拌します。二液タイプは作った分をその時に使い切らなければなりません。プライマーを塗布した下地に通気緩衝シートの敷設、水蒸気を発散させる脱気筒を取り付けて、ウレタン塗膜防水の一層目を施工していきます。


一層目の施工後、一日をあけて二層目のウレタン防水塗膜を塗布していきます。通常のペンキの塗装とは異なり、粘度の高い液体を床に流して均していくような作業です。一缶で塗れる面積もペンキとは異なり防水工事は材料も多く使用します。塗膜の厚みが全く違うからです。防水工事が高額になってしまうのは、この材料が多く必要となる事、一日で作業できることが限定されてしまう事による人件費が理由です。


二層目のウレタン塗膜防水が乾燥するのをやはり一日程待ってから、表面保護のトップコートを塗布して作業は終了となりました。
工事終了

屋上の防水工事は終了いたしました。まずは雨漏りがしなくなること、安心して屋上に出れるようになったことでK様もご安心されておりました。防水工事を行いながら外壁の状態も確認をさせていただき早めに外壁塗装を行われることもご提案させていただきました。
記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。
街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。
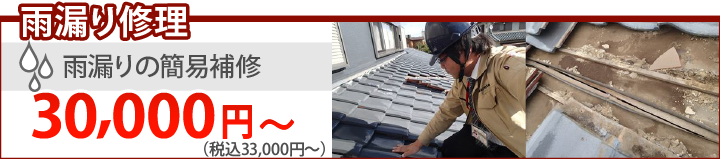


文京区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!
関連動画をチェック!
防水工事で雨漏り防止!陸屋根・屋上のチェックポイント【プロが解説!街の屋根やさん】
今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!
こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。
お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。
このページに関連するコンテンツをご紹介
ウレタン防水とは?メリット・デメリットとバルコニー・ベランダや陸屋根(屋上)への施工工程
バルコニーやベランダ、陸屋根(屋上)への防水対策として現在最も一般的なのが、ウレタン防水です。 「ベランダにウレタン防水をすすめられたけれどどんな工事なの?」 「ウレタン防水の耐久性は?見積りをもらったけれど費用は妥当?」 「他の防水方法と比べてどうなの?」 とお悩みではありませんか? …続きを読むトップコート塗り替えで防水メンテナンス!時期や費用は?
・ベランダやバルコニーの床が古く劣化してひび割れ始めている ・屋上の防水面が色褪せてきたように見える そろそろ防水のメンテナンスの時期?でも費用はどれくらいかかるのだろうか? 屋上やベランダなどの防水を放置すると、劣化で雨漏りを引き起こしそれこそ補修費用が高くなってしまうかもしれません。 …続きを読む防水性能No.1!FRP防水をおすすめできる5つの理由
漫画でページの内容を先読み! ベランダやバルコニーからの雨漏りでお困りの方、二度と雨漏りさせたくない方、そんな方にご紹介するのがFRP防水です。 このページでは、 ・ベランダやバルコニーの雨漏り対策を検討されている ・防水工事の施工方法で迷っている ・業者からFRP防水をすすめられた とい…続きを読む【防水工事】ベランダ・バルコニー・陸屋根に!種類を比較
漫画でページの内容を先読み! 防水工事とは、ベランダやバルコニー、屋上(陸屋根)に必要な、雨漏りを防ぐ工事です。 現代は戸建て住宅でも、屋根が屋上(陸屋根)になっているお住まいや、大きなルーフバルコニーがあるお住まいが増えました。 元々防水工事がされていても、年月とともに劣化してしまいま…続きを読む



- 電話 0120-989-936
- 株式会社シェアテック
- 〒222-0033
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら
街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例
- 【八王子市久保山町】バルコニーを長く守る!ウレタン防水通気緩衝工法による安心の防水工事
-


【施工内容】
防水工事
- 足立区島根にて笠木交換工事でパラペット部分からの雨漏りを解消
-


【施工内容】
雨漏り修理
- 【世田谷区下北沢】集合住宅の屋上防水のメンテナンスをウレタン防水で実施しました
-


【施工内容】
防水工事
文京区と近隣地区の施工事例のご紹介
- サンルーム屋根が強風で破損、ポリカ平板交換で安心を取り戻した施工事例
-


【施工内容】
その他の工事
- 強風でベランダ屋根の波板が破損!北区赤羽で行った波板交換工事の施工事例をご紹介
-


【施工内容】
その他の工事
- セメント瓦の雨漏りを解決した屋根部分葺き直し工事の施工事例(豊島区長崎)
-


【施工内容】
屋根葺き直し