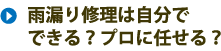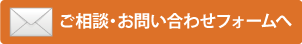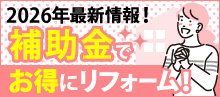調布市下石原にて棟の取り直し工事を行わせていただきました、棟の取り直しは税込18,150円/mから承っております
【施工前】

【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】

担当:木下
調布市下石原にお住いのお客様よりお問い合わせいただき屋根の現地調査にお伺いしたことが工事のきっかけになりました!
既存の屋根材は瓦屋根で、棟瓦のズレが気になるとのことでお問い合わせをいただいたようです。
瓦屋根はよくメンテナンスがいらないという事を耳にするかもしれませんがそのようなことはありません(>_<)
時期ごとにメンテナンスが必要になりますので定期的な点検を怠らないようにいたしましょう!
瓦屋根のメンテナンスを行う箇所で最も早く時期がやってくるのは漆喰でしょう。
漆喰の役割は多くありますが、メインは棟瓦の隙間を埋めて中に水が廻らないようにすることです。
そのため漆喰に不具合が生じると最悪のケース雨漏りにつながってしまうこともあります。
雨漏りを起こしてしまうと他の箇所にも影響が生まれてしまいますので十分な注意が必要です!
今回はお客様のご意向もあり、棟の取り直し工事を行わせていただきました。
新規の漆喰には南蛮漆喰を使用して防水性を向上させましたのでしばらくは安心です(^^)/
調布市下石原にお住いのお客様よりお問い合わせいただき屋根の現地調査にお伺いしたことが工事のきっかけになりました!
既存の屋根材は瓦屋根で、棟瓦のズレが気になるとのことでお問い合わせをいただいたようです。
瓦屋根はよくメンテナンスがいらないという事を耳にするかもしれませんがそのようなことはありません(>_<)
時期ごとにメンテナンスが必要になりますので定期的な点検を怠らないようにいたしましょう!
瓦屋根のメンテナンスを行う箇所で最も早く時期がやってくるのは漆喰でしょう。
漆喰の役割は多くありますが、メインは棟瓦の隙間を埋めて中に水が廻らないようにすることです。
そのため漆喰に不具合が生じると最悪のケース雨漏りにつながってしまうこともあります。
雨漏りを起こしてしまうと他の箇所にも影響が生まれてしまいますので十分な注意が必要です!
今回はお客様のご意向もあり、棟の取り直し工事を行わせていただきました。
新規の漆喰には南蛮漆喰を使用して防水性を向上させましたのでしばらくは安心です(^^)/

担当:木下
- 【工事内容】
- 瓦屋根工事
- 【工事詳細】
-
- 使用材料
- 施工期間
- 3日間(足場の架け払いを除く)
- 築年数
- 築30年以上
- 平米数
- 棟10m
- 施工金額
- 75万円(足場代含む)
- お施主様
- K様邸
- ハウスメーカー
- ハウスメーカー不明
- 保証年数
- 保証はお付しておりません
- 【工事内容】
- 瓦屋根工事
- 【工事詳細】
-
- 使用材料
- シルガード(白)
- 施工期間
- 3日間(足場の架け払いを除く)
- 築年数
- 築30年以上
- 平米数
- 棟10m
- 施工金額
- 75万円(足場代含む)
- お施主様
- K様邸
- ハウスメーカー
- ハウスメーカー不明
- 保証年数
- 保証はお付しておりません
棟瓦がずれているとのお問い合わせでした
調布市下石原にお住いのお客様よりお問い合わせいただき、現地調査にお伺いしたことが工事のきっかけになりました!

既存の屋根材は瓦で、お客様曰く瓦のズレなどが気になってきたのでそのあたりを見てもらいたいとのことでした。
今回はところどころの瓦のズレと漆喰の劣化、銅線の断裂が確認出来ました。
防水紙も劣化しておりましたがご、予算の兼ね合いもあり今回は棟の取り直し工事を行わせていただくことになりました!

瓦の屋根はメンテナンスがいらないと思われておりますが、実状そのようなことはございません(>_<)
確かに瓦本体は非常に丈夫なので塗装などのメンテナンスは必要ありませんが、他の箇所はそうはいきません!
例えばスレート屋根などと同様防水紙のメンテナンスはもちろん必要になりますし、瓦屋根特有のものですと漆喰のメンテナンスが必要になります。
漆喰という言葉は耳にしたことがある方も多いかもしれませんね。
しかし漆喰がどのようなものなのか、どういった役割があるのかご存じな方は少ないのではないでしょうか。
まずは漆喰について少しご説明できればと思います!
【目次】
1.漆喰とは
漆喰(しっくい)は、瓦屋根の一部で、瓦と瓦の間や瓦と屋根の構造材の間に使用される建築材料です。
漆喰は通常、石灰と砂、水を混ぜて作られます。この混合物は、均一に塗布され、漆喰が乾燥し硬化すると、瓦と構造材を包み込んで屋根を保護します。
漆喰は一般的に白色または淡い色を持ち、日本の伝統的な建築に特に一般的ですが、他の地域の建築でも使用されることがあります。
近年では漆喰にシリコンを混合して防水性を高めた南蛮漆喰がよく使用されるようになりました!
2.漆喰の役割
漆喰の役割は以下の3点になります。
- 防水: 漆喰は水をシーリングし、雨水や湿気が建物内部に浸入を防ぐ
- 耐久性: 漆喰は瓦とその下の構造材を保護し、屋根の寿命を延ばす。
- 美観: 漆喰は瓦屋根の外観に貢献する。
主な役割は雨風からお家を守るという事ではありますが、日本古来のトラディショナルスタイルを演出しているのも漆喰になります
3.漆喰のメンテナンス方法
漆喰のメンテナンス方法は大きく分けて3種類になります。
・漆喰の増し詰め
・漆喰詰め直し
・棟取り直し
まずは既存の漆喰のダメージが小さい場合ですが、漆喰の増し詰めです。
漆喰の増し詰めとは既存の漆喰の上から新しい漆喰を詰めていく工法になります。
とにかく工事に金額をかけたくないがひび割れは気になるというケースの場合に行います。
しかしこの増し詰めという工事はあまりお勧めできる工法ではありません。
といいますのも、古い漆喰を残したままになるので地震などで漆喰に動きが加わると古くなった漆喰が新しい漆喰ごと剥がれてしまうことがあります(>_<)
また、厚みが出てしまうのでのし瓦からはみ出して劣化が早くなったり、雨水を巻き込んで雨漏りを誘発してしまうこともあります。
飛び込みの業者などはこの工事を勧めてくることもありますが、
よほどの場合ではない限りはこちらの工事はお勧めできません!
続いては漆喰の詰め直しです。
漆喰の詰め直し工事は上記の漆喰増し詰めと異なり既存の漆喰を撤去して詰め直しを行うので上記のようなリスクは少なくなります。
こちらの工事を行うケースは棟自体に歪みや銅線が切れたりしては無いが、漆喰だけひび割れや剥離が生じてしまっているという場合です。


純粋に漆喰のメンテナンスを行う工事ではありますが解体作業を行う関係上多くの場合は足場の仮設が必要になります。
漆喰を解体していくと中の盛り土がボロボロと出てきてしまいます。
瓦は通常時でも滑りやすい屋根材なので砂ぼこりがあるだけでかなり危険度が増してきます。
職人の安全を十分に考慮させていただき工事のご提案をさせていただきますので、その旨あらかじめお含みおきいただけますと幸いです(^^)/
最後に棟の取り直し工事です。
棟の取り直し工事は棟瓦のメンテナンスとしては最上級の工事になります。
既存の棟をバラして漆喰を詰め直してのし瓦を積んで銅線も巻きなおすことができるので歪みなどの補正もできます。

また、盛り土を完全に撤去して南蛮漆喰を代替品として使用することもできますし、乾式工法といってハイロール(馬場商店)という防水性の高いシートを使用して漆喰の代わりに置き換える工法も可能です。

乾式工法は屋根の重さを軽減することもできるので耐震性の向上も望めます。
例:大棟1箇所(10m)湿式工法(漆喰)→乾式工法(ハイロール)への変更の場合
湿式工法:10kg/m×10m=100kg→乾式工法:0.6kg/m×10m=6.0kg
約16分の1の重さになります!
4.工事の流れをご紹介
それでは最後に工事の流れのご紹介です。
棟の取り直し工事は以下の3工程で行ってまいります。
・既存棟バラシ
・のし瓦の積み直し(漆喰の施工)
・冠瓦の施工
まずは既存の棟をばらしていきます。
棟をバラして既存の盛り土の撤去を行ってまいります。
この際は上記にも記載した通り滑りやすいので注意が必要です。


のし瓦や冠瓦は再利用いたしますので大事に保管しましょう。


解体が完了して清掃した後は新しく棟を積んでいきます。
新しく使用した漆喰は馬場商店のシルガード(白)を使用しました。

シルガードは従来の漆喰にシリコン樹脂を混合して防水性を向上させた製品で白と黒の2色がございます。
白のシルガードは施工後の見た目が良いのですが黒に比べると材料費が高くなります。
大棟など人目に触れやすい箇所では白を使用することが多いですが、特に気にしないとのことでしたら黒を使用することで材料費を多少ですが落とすことができます!
今回は既存のものに合わせたいとのことだったので白を使用いたしました。

漆喰を詰める際はのし瓦の外部末端から15~30mmぐらいになるように詰めていきます。
それ以上出してしまうとのし瓦を伝った雨水が巻いてしまい漆喰の劣化を早めてしまいますのでご注意ください。
漆喰を詰めながらのし瓦を積んでいき冠瓦をかぶせて完了になります。


銅線は中を通すようにしておりますので切れにくい造りになっております。

瓦のズレも直せる分直して施工完了になります。
棟の取り直し工事は税込18,150円/mから承っております(足場代別途、のし3段まで)。
施工する棟の本数やのし瓦の段数によって価格は変動いたしますので詳しくはお問い合わせください!
街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。
工事を行なったK様のご感想をご紹介いたします
K様のアンケート
【工事前】

- Q2.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?
- 築何十年も経っているため。その間屋根を直しておらず、不具合が目立ってきてるので。
- Q3.弊社をどのように探しましたか?
- インターネット 屋根専門の会社 近くに事務所があること
- Q4.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?
- すぐに問い合わせた
- Q5.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?
- 屋根専門の業者さんにお見受けしたので
- Q6.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?
- しっかり見てくれていたと思う
【工事後】
- Q2.当初、工事を依頼する会社にどんなことを期待されていましたか?
- 単なるリフォーム会社でなく屋根専門の業者さんに頼もうと思っていました。
- Q3.弊社にご依頼いただく際に他社と比較しました方はどこの会社と比較しましたか?
- 地元の屋根屋さん
- Q4.弊社に工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?
- 料金 工期 日本人の職人さんが作業すること
- Q5.工事が終わってみていかがですか?良かった事・嬉しかったことを忌憚なく頂戴出来ましたら幸いです。
- 職人さんの手際連携が良く、仕上がりもしっかりしていた。
- Q6.街の屋根やさんを他の方に紹介するとしたらなんと紹介しますか?
- ネットonlyだが仕事はしっかり
K様のアンケートを詳しく見る→

調布市ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!
関連動画をチェック!
瓦屋根の雨漏り原因とは?屋根の構造をもとに詳しく解説!【アメピタ!】
今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!
こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。
お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。
このページに関連するコンテンツをご紹介
重くて固い瓦の落下は二次被害を招きます、だからメンテナンスが超重要
漫画でページの内容を先読み! 台風や地震が多い昨今、瓦屋根に不安を感じていませんか? 重くて固い瓦が落下すると、まず間違いなく落下地点のものを傷つけ、破壊します。 自分の敷地内ならまだしも、お隣に落ちて何かを壊したとなれば目も当てられません。 重くて固い屋根材だからこそ、必要なメンテナ…続きを読む



- 電話 0120-989-936
- 株式会社シェアテック
- 〒222-0033
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら
街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例
- 瓦屋根の雨漏りを葺き替え工事で根本解決|稲城市押立で軽量・高耐久屋根材に変身です!
-


【施工内容】
瓦屋根工事
- 瓦屋根の棟補修と漆喰詰め直しで雨漏りを未然に防ぐ!【葛飾区新小岩の施工事例】
-


【施工内容】
屋根補修工事、瓦屋根工事、漆喰詰め直し
- 狛江市中和泉にて瓦からスレートへの葺き替え工事を税込126万円で行わせていただきました!
-


【施工内容】
瓦屋根工事
調布市と近隣地区の施工事例のご紹介
- 世田谷区下北沢の4階建てマンションで実施したバルコニーウレタン防水工事|大規模改修で雨漏りリスクを徹底軽減
-


【施工内容】
防水工事
- 世田谷区駒沢にて訪問業者に指摘を受けたスレート屋根をカバー工法にて工事致しました!屋根材にはスーパーガルテクトを選定致しました!
-


【施工内容】
屋根カバー工法
- 世田谷区若林にて劣化した塩ビ波板をポリカーボネート製の波板へ交換工事をおこないました!
-


【施工内容】
その他の工事