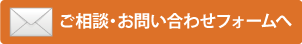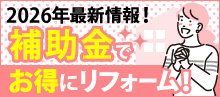東大和市蔵敷で瓦屋根の谷樋交換、銅製からカラーステンレスへ
【施工前】

【施工後】
【お問い合わせのきっかけ】

担当:岡野
「金属製の谷樋が傷んできているようなので交換してほしい」と東大和市蔵敷のお客様からご相談がありました。谷樋は前述のように金属製のものが多く、そのため『谷板金』と呼ばれることもあります。一般的な雨樋は屋根の外周である軒先に取り付けられていますが、谷樋は屋根の面が谷状になった部分、屋根そのものの上に設けられるため、雨水が浸入しやすい部分です。早めのメンテナンスを心掛けたい部分でもあります。

担当:岡野
- 【工事内容】
- その他の工事 谷樋交換工事
- 【工事詳細】
-
- 使用材料
- 施工期間
- 5日間
- 築年数
- 23年
- 施工金額
- 詳しくはお問い合わせください
- お施主様
- G様邸
- ハウスメーカー
- ハウスメーカー不明
- 保証年数
- 【工事内容】
- その他の工事 谷樋交換工事
- 【工事詳細】
-
- 使用材料
- カラーステンレス谷板金
- 施工期間
- 5日間
- 築年数
- 23年
- 施工金額
- 詳しくはお問い合わせください
- お施主様
- G様邸
- ハウスメーカー
- ハウスメーカー不明
- 保証年数
【東大和市蔵敷で瓦屋根点検】


塗装の必要がない和瓦を使用した東大和市蔵敷のお客様邸です。美しい緑青色をしていることから分かるように銅製の谷樋を使用しています。新品の銅は同じく銅が主成分であるピカピカの10円硬貨のような色をしているのですが、使用しているうちに酸化していき、このような色になります。神社や仏閣で見る銅屋根と同じです(東大和市蔵敷1丁目419の蔵敷熊野神社の屋根にも銅屋根が使用されているようですね)。一旦、酸化してこの色になると強固な酸化被膜となり、これ以上の参加や腐食を防止するのですが、こちらの谷樋は浸食が進んでいるようです。


谷樋には穴が開いている部分もありました。ここから雨水が浸入していくのでやがては雨漏りに繋がります。銅製の雨樋は20年以上、環境によっては30年以上の耐用年数があると言われていますが、そこまで持たないケースもあるようです。原因は局地的な酸性雨とも、釉薬瓦にの釉薬に含まれている鉄分の為とも言われています。

それにしてもお施主様のお家は立派なものです。大きなお家で、しかも平屋という贅沢さ、いぶし瓦の色を再現した釉薬瓦、本格的な和風の造り、素人の私が撮影した上の画像でもその立派さが伝わると思います。
【施工の様子~銅製谷樋をカラーステンレス製へ変更】


今回の谷樋の交換工事ですが、傷んでいる部分はカラーステンレス製のものへと交換し、傷みの少ない銅製雨樋は再利用ということになりました。谷樋の交換はちょっと大変です。ほぼ剥き出しとなっている普通の雨樋とは違い、部分的に瓦に覆われているところも多いため、その瓦を解体していかなければならないからです。解体していくと鳥の巣が出てきました。ある程度、年数が経った瓦屋根の下には鳥の巣が作られていることが多いですね。巣立った後のようなので、撤去します。


板金で作られている谷樋を外すとその下には防水紙が敷かれています。穴の開いた銅製の雨樋の部分から雨水が浸入していたようで、防水紙には穴が開いていました。その下地の木製の部分はまだ変色していませんから、穴はできたばかりなのでしょう。このタイミングで谷樋交換ができてよかったです。新しい防水を敷いて雨水が浸入しないようにします。


カラーステンレス製の谷樋を設置して、瓦を再度、積み直します。瓦を積む前と積んだ後を較べると、意外に谷樋が大きいことが分かります。これで健全な屋根になりました。
【竣工~銅製谷樋をカラーステンレス製への変更】

傷んでいない銅製の谷樋も再利用しました。棟のすぐ下にある緑青色の谷樋が銅製の部分です。なんでも新しくすればよいというものではなくて、使える部分は再利用するというのはこれからの時代を生きる私達に課せられた使命のようなものです。こちらのお家の谷樋はステンレス製になりましたので、銅製と同じくらい長持ちするでしょう。
記事内に記載されている金額は2021年05月13日時点での費用となります。街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!
火災保険が適用できる?屋根工事・屋根修理【プロが解説!街の屋根やさん】
今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!
こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。
お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。
このページに関連するコンテンツをご紹介
瓦屋根の特徴を徹底解説!メリット・デメリットなど瓦屋根の総合ガイド
日本の屋根と言えば、誰しもが思い浮かべる瓦屋根。伝統的なイメージがある反面、近年では「重くて地震に弱い屋根」という印象も強くなってきています。そんな瓦屋根ですが、姿はそのままでありながら時代に合わせて軽量化が進められているように、変化を繰り返していることはご存知でしょうか。それには「地震への強さ」…続きを読む粘土瓦・コンクリート瓦・セメント瓦、 瓦の種類・見分け方とメンテナンス方法
古くから使用されている屋根材、それはなんといっても「瓦」でしょう。皆さんが瓦と言ってイメージするのは寺社仏閣のような和風建築のものですか?それとも地中海風の建物に見られるオレンジ色のグラデーションのかかった屋根でしょうか?瓦屋根はその形状により分類もできますし、使用している材質によっても分類でき…続きを読む瓦屋根のさまざまな補修とリフォームの費用と価格
街の屋根やさん東京ではお客様にご安心とご満足いただけるよう10のルールを定めました。スタッフ一同、このルールを厳守し、お客様がご納得されるサービスを提供することを。お約束いたします。…続きを読む知ってお得!屋根の便利な豆知識
普段に何気なく眺めている屋根ですが、近所のお住まいを見渡しただけでも、様々な形、様々な材料が使われていることが分かと思います。 また、グーグルアースなどでは世界中の屋根を眺めることができます。素敵なデザインのものもあれば、ユニークでかわいらしいものもあります。屋根の勾配とデザイン屋根の勾配が緩やか…続きを読む



- 電話 0120-989-936
- 株式会社シェアテック
- 〒222-0033
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 2F

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら
街の屋根やさんは東京都以外にも神奈川県、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例
- サンルーム屋根が強風で破損、ポリカ平板交換で安心を取り戻した施工事例
-


【施工内容】
その他の工事
- 足立区千住元町にて波板交換!劣化した塩ビ波板を耐久性に優れたポリカ波板へと交換工事を行いました。
-


【施工内容】
その他の工事
- 世田谷区若林にて劣化した塩ビ波板をポリカーボネート製の波板へ交換工事をおこないました!
-


【施工内容】
その他の工事
東大和市と近隣地区の施工事例のご紹介
- 小平市学園東町で行ったレサス屋根の葺き替え工事レポート(税込286万円・足場、外壁塗装、防水工事含む)
-


【施工内容】
屋根葺き替え
- 立川市富士見町にて雨樋の部分交換工事を(税込220,000円)行わせていただきました!
-


【施工内容】
雨樋交換
- 東村山市恩多町にて税込1,470,000円(足場代別途)で太陽光パネル撤去と屋根のカバー工事を行わせていただきました!
-


【施工内容】
スレート屋根工事